山口県の徳地少年自然の家で、テクニカルロープレスキューの講習会を実施しました。
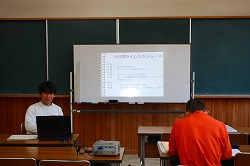
机上講習の様子
倍力効果は、平地で基本を行い、山で応用を行います。

まずは基本から

9倍力の応用
壁面では、器具を使った懸垂降下や上昇を実施

アメリカ式、ヨーロッパ式など全く関係なく基本を行いました。
レスキュー3はアメリカ式という声をちらほら聞きますが、それぞれの利点や
欠点などの特徴を理解すれば、混乱や恐れることはありません。
情報に振り回されないように、ぜひ基本的な考え方をしっかり身に付けて下さい。

ロープを展張したハイラインシステムも実施します。
伸び率の高いよりロープと違い、伸びないスタティックロープを使ったハイラインシステムではいくつかの守るべきルールがあります。
今回参加した皆さん、ポイントしっかり理解して忘れないで下さいね。
夜間は、交流会を実施して、他の消防組織の方との飲みにケーションを図りました。
今回もいろいろな情報を交換出来き大変有意義な時間でした。
また、今回は、過去にコースを受講して頂いた2名の方がプラクティス(練習)参加してくれました。
お二人とも以前と変わらずお元気で変りの無い様子でした。
あっという間の3日間で楽しく学べました。
4月13日からのテクニカルロープレスキュー岡山や3月27日からのテクニカルロープレスキュー京都もまだ募集しておりますのでロープレスキューのスキルアップにぜひご利用下さい。
過去に受講済みの方のプラクティス参加も大歓迎です。
ご希望の方は、info@rescue-japan.com
までお問い合わせください。







